中国化学産業を取り巻く状況と方向性を踏まえれば、日本企業にとっては、中国産の余剰製品によるグローバルでの低価格攻勢・海外輸出は各国政府の阻害があれど、今後も続くという前提を持つことが大切な状況。その上で、価格競争力を磨き、コモディティ品で勝負ができる体制を築くか、技術を磨き更なるハイエンド領域に染み出していくか大胆な方向性へのシフトが期待される。


収益性に基づく低PBR日系化学企業の類型化と企業価値向上策
低PBRの日本化学企業が価値向上を図るにはIR戦略の高度化、事業ポートフォリオ再編、企業を超えたスケールメリットの追求の3つに類型化し得る
本稿は「 日系化学企業の低PBRの現状と提言 」の続編です。
日本の化学企業は、PBRが恒常的に1倍を下回る企業が一定数存在しており、海外プレイヤーと比較しても依然として低位に留まっている。PBRの水準が示す通り、市場からの評価が十分に得られていない企業は多いが、その背景は一様ではなく、収益性の高低によって異なる構造的課題を抱えているケースが多い。実際、低PBR群の中にも業界平均を上回るEBITDAマージンを誇る企業は少なくない。
本稿では、PBRと収益性の2軸で企業群を分類し、
- (A)高収益だがPBRが低い企業
- (B)低収益かつPBRも低い企業
PBR 低水準企業における収益性の分布と戦略的含意
EBITDAマージンとPBRの2軸で日系化学メーカー各社を分析した結果、PBRが1.0を下回る企業59社のうち、EBITDAマージンが業界平均(13.7%)を上回る企業は14社にのぼることが確認された。すなわち、同一のPBR水準に分類される企業群であっても収益性にはばらつきが有り、PBRが低くとも一様に収益性が低いとは限らない実態が明らかとなった。
このような環境下においては、PBRが1.0を下回る企業であっても、その収益性に応じてPBR向上に向けた戦略的アプローチを柔軟に変化させる必要があると考えられる。以下では、収益性の水準に応じて、(A)PBRが低水準かつ高収益の企業、(B)PBRが低水準かつ低収益の企業、という2つの象限に分類し、それぞれに対する戦略的方向性を検討する。
「日本化学業界のこれまでの慣習や通例を見直す潮目にあると捉え、自社のビジネスモデルや戦い方を再定義する事をお勧めする」
A. PBRが低水準 × 高収益
この領域に位置する企業は、足元では高い収益性を確保している一方で、PBRが1.0を下回っており、市場評価との間に乖離が生じている。こうした企業群は、財務実績に対する投資家の理解や期待が十分に形成されていない可能性があり、場合によってはM&Aの潜在的な対象と見なされるリスクも内包している。
そのため、当該企業群においては、現在の高収益性が一過性のものではなく、将来にわたって持続的に成長していくストーリーを明示的に説明することが求められる。具体的には、決算説明資料やプレスリリース等を通じて、高収益の源泉や事業の構造的強み、および将来に渡り企業が成長していく事に関する説明を行うことが一つの方策と考えられる。また、中期経営計画においては、現状の利益水準を起点に、どの市場領域や製品カテゴリへ資本を再投下し、どのようなスケールアップを志向するのかといった定量的な成長戦略の提示が重要となる。
これらの取組みによって、企業は自社の収益力と成長性に対する投資家の理解を促進し、市場評価の是正につなげることが期待される。
B. PBRが低水準 × 低収益
この象限に位置する企業は、PBRと収益性の双方において低水準にある。これらの企業は、さらに
- (B-1)定性的には一定の事業基盤を有するが、複雑な事業ポートフォリオや資本効率の低さにより企業価値が毀損されている企業群
- (B-2)事業の成熟化等により業績が長期にわたって停滞しており、明確な打開策が見出せていない企業群
B-1. 定性的には優良だがコングロマリット・ディスカウントが生じている企業
このタイプの企業には、総合化学メーカーなどが含まれ、競争力ある個別事業を有するものの、企業全体としての一貫性や戦略性が希薄であり、結果として市場からの評価を得られていないケースが多い。
特に、日本企業に未だ残る終身雇用制度や家族的経営意識といった文化的背景に加え、ケミカルチェーンの切り離しに伴う一時的コストへの懸念などから、成熟・衰退期にある事業を一定程度抱え続けている企業も依然として多く、こうした構造的要因が事業ポートフォリオの再編を困難にしている面もある。
こうした企業においては、事業ポートフォリオの再編や非中核事業の分離・売却等を通じた構造改革に加え、財務レバレッジの適正な活用を通じた資本効率の改善が求められる。加えて、再編後の重点領域として高付加価値事業に経営資源を集中させる方針を明確にし、それらの戦略的方向性を適切に対外発信することで、企業価値の再評価を促すことが期待される。
なお、近年では、特定の総合化学メーカーが実際に事業分社化を進めるなど、企業価値向上に向けた取り組みが徐々に現れつつある。さらに、M&Aによって獲得した事業を的確に育成し、新たな高付加価値領域の事業柱として定着させている企業も存在する。このような企業においては、事業ポートフォリオを動的に再構成する能力そのものが株式市場から高く評価されており、現時点での収益性が必ずしも高くない場合でも、将来成長に対する期待が反映されるかたちで、PBRが相対的に高水準となっているケースが見られる。
B-2. 事業の成熟化により業績が停滞し、打開策が見えにくい企業
この区分に該当する企業では、構造的な収益性の低さに加え、外部環境や経営資源の制約により抜本的な改革が進みにくい状況が継続している。こうした企業に対しては、業界内外での統廃合や他社との連携を通じてスケールメリットを確保し、固定費構造の見直しや収益モデルの再構築を図る必要がある。中長期的なバリューアップを実現するためには、一定のリスクを取った経営判断が不可欠である。
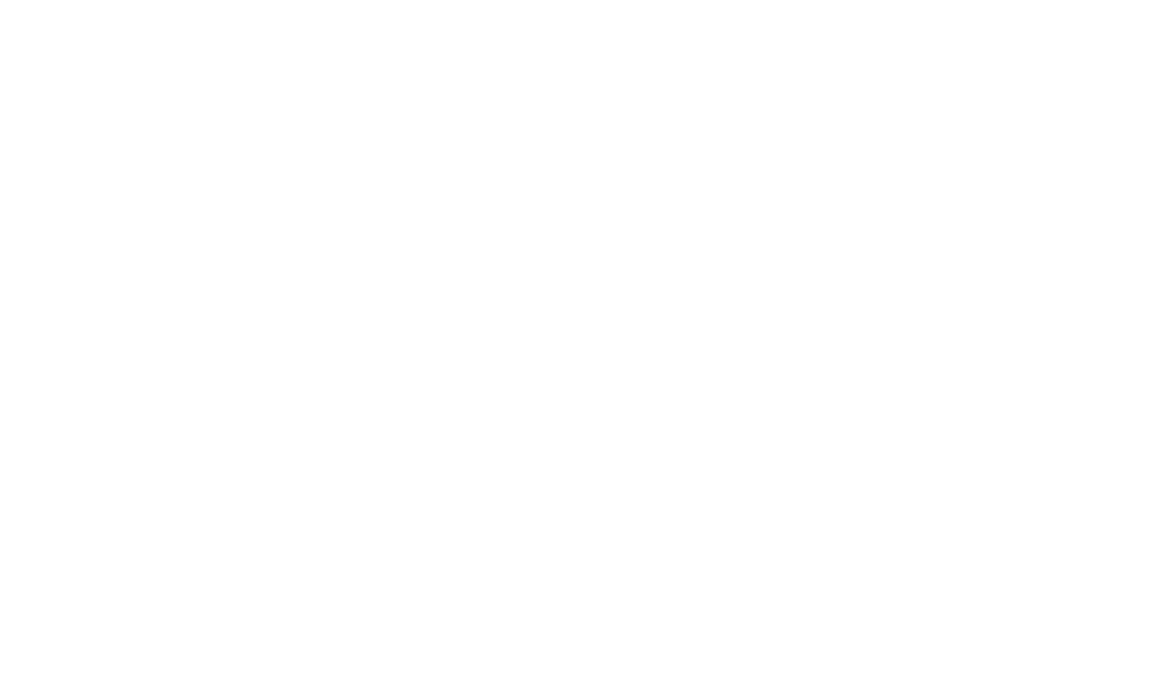

_image_caption_none.jpg?v=1687234)
2_image_caption_none.jpg?v=1687234)


